日本では年がら年中桜餅が売られている印象がありますが、桜と言えば春の花。あの独特の香りがする葉と甘いお餅のコンビネーションがたまらない、日本を代表する、和菓子を代表する一品ではないかと思います。
だがしかし、我が家の近所、台湾で桜餅を入手することは困難であります。そこで自作したのですが、見事に失敗して、もろもろ学んだことがあるのでそれを書き記します。
目次
桜餅の作り方

簡単に書けば、桜餅(道明寺)は以下の手順で作られます。詳しいレシピは和菓子屋さんなどが公開しているものを参照してください。
- あんこを丸める
- お湯に食紅、砂糖を溶かしたもので道明寺粉(乾燥)を戻す
- 桜の葉の塩漬けは水かお湯につけて塩抜きし、用意しておく
- 戻した道明寺粉をあんこにまとわせ、桜の葉をまけば完成
桜の葉の塩漬けも自作

桜の葉の塩漬けが売られているのをここ台湾では見たことがありません。SOGOの地下とかに売られているのでしょうか。ないものは自作します。
出来上がった桜の葉の塩漬けは塩抜きして準備完了です。
餡子(あんこ)の作り方

我が家の近所ではこしあんなどという高尚なものは売られていません。そこで、小豆から作ってもいいのですが、小豆の甘露煮から作ると多少時間が短くなります。小豆の甘露煮なら近所のスーパーで売られています。
小豆の甘露煮をザルで濾し、濾したものを火にかけて水分を飛ばします。この時、多少乾燥するぐらいまで水分を飛ばさないと、丸める時にべとべとになってしまい、うまく丸くできません。過去にそれで何度か失敗しています。この時の乾燥具合は結構しっかり目がポイントです。
しっかり水分を飛ばしたらバットなどに上げ、粗熱をとって、ラップなどで密閉して冷蔵庫に入れておきます。
豆から作る場合
豆から餡子(あんこ)を作る場合、しっかり柔らかくなるまで煮るには、豆のサイズが大きくなるほど時間がかかります。
以前餡子を作った時、皮を剥いてから裏ごしするのが面倒でバーミックスで粉砕したのですが、しっかり煮えてなかったのかちょっと硬い粒々が国の中に残る、食感の悪い餡子になったことがあります。
ああ、じゃあ小さい豆の方が良いかなとも思うのですが、こしあんにしたい場合は逆にサイズが大きい方が皮むきが簡単だったりします。
大きい豆も小さい豆も餡子を作る場合はちゃんと柔らかくなるまで煮ることが重要です。
道明寺粉を自分で作る
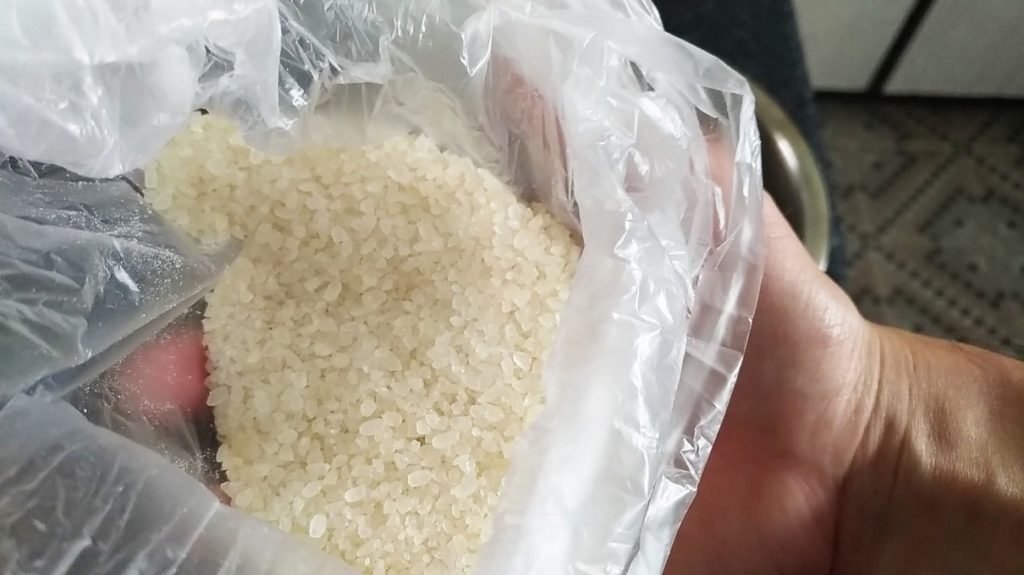
道明寺粉には種類があって、通常の道明寺粉や頭道明寺粉と呼ばれるものがそれです。どのぐらい小さく砕いた状態かでわけるようです。
頭道明寺粉と道明寺粉
頭道明寺粉の特徴としては、道明寺粉よりも頭道明寺粉の方が粒が細かい分、戻すときに戻りやすいという特徴があります。味の違いは感じませんが、細かい分多少食感の違いが発生します。好みで使い分けをしても良いですが、そもそもの作業工程の違いによっても使い分ける必要があります。
例えばレンジなどを使ってしっかり火を通す場合には通常の道明寺粉でも問題ないと思います。しかし、例えばお湯を入れて放置するだけのようなレシピの場合、通常の道明寺粉を使うと芯が残った、硬い状態のままになってしまいます。実は今回、この失敗をしました。

道明寺粉の原料
道明寺粉は基本的にもち米を砕いたものです。
道明寺粉の作り方
もち米を2時間程度浸水し、その後30~40分蒸します。そして蒸しあがったもち米をクッキングシートの上に広げ、2日ぐらいかけて完全に乾燥させ、最後にミキサーで粉砕します。
バーミックスのスーパーグラインダーを使って粉砕したのですが、長くやると細かくなりすぎるし、ちょっとだけだとかなり粒が残ったままになってしまいます。ちょうどよい加減が難しく、道明寺粉と頭道明寺粉、さらには小さくなりすぎた粉状のもち米が混ざったような状態となりました。
道明寺粉の戻し方
お湯を入れるだけでレンジを使わないレシピもありますが、粒の大きさが大きいと芯が残ります。
日本ではレンジが普及していますので、そんなに困る方もいないのかも。レンジがない、しかも粒が大きい道明寺粉を使う、という我が家のような場合は、鍋で火を入れながら戻すのが良かったのかもしれません。お湯を入れて、混ぜてから蒸らすだけでは芯が残ってしまい、食べにくかったです。
道明寺粉に投入する水の量はおおむね乾燥道明寺粉の重量の2倍。ただし、その2倍の水量の中に糖分も含ませます。いわゆる砂糖水ですが、例えばコーラは100mlに対して11g程度の砂糖が含まれています。甘露煮などのシロップの場合、水量に対して約半分の重量、つまり、水100mlに対して50g程度の砂糖が入っていることが多く、好みによってさらに多くの砂糖を入れる場合もあります。液体に対する砂糖の量が増えれば増えるほどトロミも増します。
レンジを使う場合もお湯だけで戻す場合も、鍋で加熱しながら戻す場合も、甘さ加減の参考にすると良いと思います。特に鍋で戻す場合は蒸発にも注意です。
鍋で戻す場合の方法
後日、鍋に道明寺粉とほぼ同量の水を入れて、ご飯を炊く要領で戻していったのですが、ちょうど良い吸水加減になったと思って鍋からおろし、味見をしたところ、それでもやはりちょっと芯が残っていました。
もちろんお湯をかけて蒸らしただけなんかよりは食べるのに耐えうる出来栄えではあったのですが、水をもっと入れるなど、もっと工夫した方が良いと感じました。
道明寺粉の着色
それから我が家には食紅もなく、着色も困りました。そこで、代用品として以前に作ったスモモのシロップを使おうと思い立ったのですが、それだけでは色が薄く、追加で乾燥ローゼルを入れて火にかけ、赤色を追加しました。
しかし、ローゼル2個だけでは十分な赤色とはなりませんでした。とはいえローゼルをたくさん入れるとローゼルの酸味が強く出るような気がして、それ以上はできませんでした。シロップの段階から生地に混ぜるまでは結構ピンクに見えたのですが、桜餅になるとほぼ真っ白。全然赤みが足りませんでした。

ローゼルの砂糖漬けシロップを利用

後日、ローゼルの砂糖漬け(といっても甘露煮のように煮込んだもの)のシロップが真っ赤だったのでそれを使って作ってみたところ、もう少し赤くなりました。
砂糖が大量に入った甘露煮のようなものなので、酸味を感じることはありませんでした。
お寿司みたいに手水を使う

さて、桜の葉の塩漬け、道明寺粉、あんこが用意できたら実際に桜餅を作りますが、戻した道明寺粉はかなりベトベトするので、手に砂糖水をつけながら作業をすると良いです。余分に付いた砂糖水はもち米が吸収するので、そんなに気になりません。この時の砂糖水は水100mlに対して100gの砂糖を入れて、火にかけて砂糖を完全に溶かし、それを冷やしたものを使用しました。
寿司を握るがごとく、まずは砂糖水で手水をして、戻した道明寺粉を手に取り、丸くし、それから平らにつぶし、真ん中に丸めたあんこを乗せ、生地で包み込み、それも丸くし、最後に桜の葉の塩漬けで包みます。今回桜餅を作った時のそれぞれの重量は以下の通りです。
- あんこ:15g
- 生地(戻した道明寺粉):30g
あんこは400g以上あったので26個、生地は乾燥道明寺粉206gを使って、18個に分けることができたので戻した状態で540g程度あったと思われます。
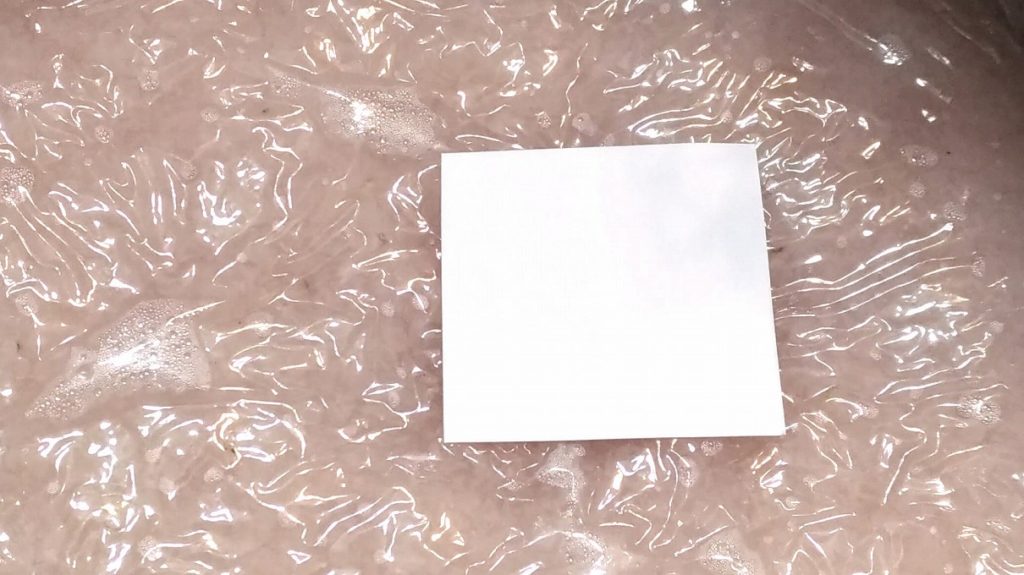
桜餅を作る際に注意した方が良いこと
今回、はじめて桜餅を作ってみて、注意した方が良いと感じたことなどを書き記しておきます。
- 桜の葉は12cmぐらいのものを使うこと
- あんこはしっかり水分を飛ばすこと
- 道明寺粉は芯が残らないようにしっかりと戻すこと
- 色付けの工夫が必要
最後に
食紅を使わずにピンク色にするための方法はまた改めて検討しようと思っています。また、今回は芯の残った桜餅になってしまったので、次回また来シーズン、桜の葉が採れて塩漬けができたころに挑戦してみたいと思っています。
